産科・小児科、さらに他科も関わり総合力で母子を救う周産期医療
当院は大阪府産婦人科診療相互援助システム、新生児診療相互援助システムの基幹病院であり、地域周産期母子医療センターの役割を担っています。通常分娩だけでなくハイリスク分娩、ハイリスク新生児の治療・ケアも行う産婦人科と小児科の連携や取り組みについて聞きました。
産前から産後まで妊産婦に寄り添う
陌間 当院は早くから周産期センターを開設し、今では当たり前になっているNICU(新生児集中治療室)の早期導入、血液型不適合妊娠の血漿交換、結合双胎の分離手術の国内2例目など、積極的に周産期医療に取り組んできました。
清水 産科のスタッフは、ほとんどが助産師で、正常分娩から医療を要するケースまで対応できる体制です。助産外来では、不安を抱えている初産婦さんや体重のコントロールがうまくいかない方など、時間をかけて医師と話すのは難しいお悩みに助産師がお応えしています。家でできる運動指導もしているので、助産外来を利用された方は体力がついてスムーズにお産できる方が多いんです。

陌間 一般的には無痛分娩、当院では和痛分娩と呼んでいるお産も行っていて、年間1000件ほどのお産のうち4分の1は和痛分娩を希望されています。陣痛が来てから硬膜外麻酔を開始しますので痛みに苦しむようなことはありません。お産後の体力を温存できますし、お産の痛みによる恐怖はかなり軽減されるはずです。少子化が問題となっている今、また出産したいと意欲につながるという意味で、和痛分娩は一定の役割を担っていると思います。

清水 当院でお産された方には、退院後にお電話でのフォローアップ(退院後1~2週間)をしているのですが、お母さんは眠れなかったり食事も摂れなかったりでとても疲れてしまって、中には鬱(うつ)になってしまう方もおられます。そんな方のお手伝いをしたいという思いから、最大6泊までご利用いただける「産後ケア」を始めました。赤ちゃんはお母さんと一緒にいることもできるし、こちらでお預かりすることもあります。授乳が上手くいかない、赤ちゃんが心配で寝るタイミングがわからないなど、いろんなお悩みの相談に応じたり練習もしているので、ぜひ利用していただきたいですね。
スピードと手厚さを兼ね備えた医療
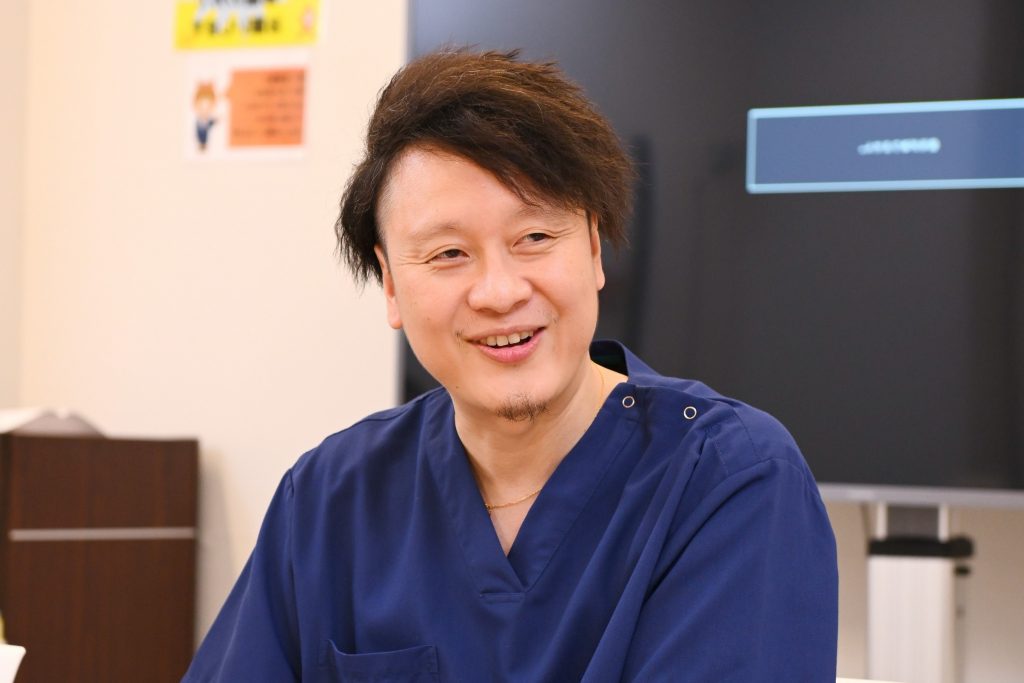
小笠原 当院では小児科の中に新生児チームを設け、NICU21床、GCU(新生児回復室)15床の体制で大阪北部の新生児搬送を受け入れています。
小畑 赤ちゃんに疾患があると予想される場合は私たちがお産に立ち合いますし、予想外の新生児仮死の場合もすぐに駆けつけます。特に当院は分娩室とNICUが隣接していて、すぐに治療を開始できる利点があります。
小笠原 新生児蘇生は産科の先生や助産師も初期の対応なら可能ですが、それ以上のことも私たちがすぐに対応できる体制です。
陌間 赤ちゃんに関わる以上、産婦人科もその知識は必要だということで、小児科の先生に新生児蘇生の講習をしてもらっています。リスクが予想されるケースについては、その後の管理や方針をあらかじめ立ててもらえるので、お母さんに事前に伝えておくことができますし、私たちも迷うことがないですね。
小畑 週に一度の周産期カンファレンスで、基礎疾患がある赤ちゃんや超未熟児として出生されるリスクのある方々の情報を共有しています。またお母さんには赤ちゃんがどんな治療を受けるか、どういった経緯をたどるかを説明する機会をもらっています。赤ちゃんに病気があるということで親子関係を築くのにハードルができることもあるので、そういったところをフォローできる場を設けてくださるのはありがたいですね。

辻本 NICUやGCUに赤ちゃんが入ると母子分離になってしまって、その間に「自分が早く産んでしまったから」と自責の念が強くなったりもするので、そういった精神面のケアもできるよう関わっています。また超未熟児の赤ちゃんは「触ると害を及ぼしてしまうかもしれない」と思われることも多いのですが、お母さん・お父さんに、触れられることで赤ちゃんは安心するんですよと声掛けしています。
清水 そういったお母さんに関して、産後ケアを勧めた方がいいか乳児看護課から相談を受けて、事前に情報をいただくこともあります。

辻本 千佳
辻本 退院を控え、不安が大きくなる方もおられるので、産後ケアをお勧めすることもありますね。
小笠原 当院には小児外科の常勤医がいるので、バックアップ体制が非常にしっかりしています。また例えば先天性気管狭窄症は耳鼻咽喉科が、口唇口蓋裂は形成外科が生まれたときから関わるなど、多くの診療科の協力を得ながら手厚く見守ることができます。
陌間 出産の高年齢化に比例して基礎疾患をお持ちの妊婦さんが増えています。他の診療科との連携で基礎疾患も含めてケアしながら安心してお産に臨めるのも、総合病院である当院の強みです。
また重篤な分娩経過をたどる妊婦の頻度は、10年前は222人に一人でしたが、分娩の高年齢化に伴い、141人に一人にまで増加していると、大阪府の最重症妊産婦受入事業報告(2023年度調整)で指摘されています。児も母体も救命する観点から、周産期センターがある当院を含む高次施設で分娩するメリットは、大きいと思っています。
取材日:2024年5月




